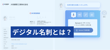2022年に"ChatGPT"が一般公開されてからというもの、"生成AI"の普及速度や進歩には目覚ましいものがあります。
既に多くの企業が様々な開発競争を繰り広げた事で、日本でも一気に"生成AI"は身近な存在となり、ビジネスの現場でも"生成AI"を業務に取り入れる企業が増えてきました。
しかし、"生成AI"による業務改善や変革への期待が高まる一方で、「どうやって仕事に取り入れればいいのか分からない」、「難しそうで、使いこなせるか不安・・・」と感じている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、"生成AI"の概要をご説明した上で、当社で導入した"Gemini for Google Workspace"を実際に社員が使用した感想や導入時の注意点をお伝えしますので、ぜひ"生成AI"の使用を検討する際のご参考にしていただければ幸いです。
"生成AI"とは
![[JP]生成AI](https://www.daiwast.co.jp/hs-fs/hubfs/images/blog/%5BJP%5D%E7%94%9F%E6%88%90AI.png?width=500&height=314&name=%5BJP%5D%E7%94%9F%E6%88%90AI.png)
"生成AI"とは、使い手がシステムに”プロンプト”と呼ばれる指示を与える事で、大規模な学習データから抽出したパターンやルールに基づき、テキスト・画像・音声・動画・プログラミングコードといったデジタルコンテンツを生成する技術です。
一口に"生成AI"といっても、その種類は多岐にわたります。
例えば、"ChatGPT"や"Gemini"のように文章生成が得意なもの、"Stable Diffusion"や"DALL-E"のような画像生成をするもの、そして"Perplexity"や"Genspark”といった検索エンジンとしての機能を意識したもの等、それぞれに特徴があります。また、無料か有料かでも機能性や操作性が大きく変わってきます。
"生成AI"が得意な業務と苦手な業務
"生成AI"は、テンプレートがある文章の作成や膨大な情報を参照するデータ分析といった業務に向いています。以下のような作業を"生成AI"に任せれば時間を節約でき、人はより重要な業務に集中できるようになります。
- 一定の形式がある文章の作成
- ルールに基づく単純作業
- 大量データの分析/予測
- 翻訳/要約
一方で、"生成AI"が苦手な分野もあります。その内容は以下のとおりです。
- 創造性や独創性の高いアイデアの創出
- 感情や意図の理解
- データ不足の事柄への対応
- 曖昧な指示や抽象的な概念の理解
- 常識や倫理観に基づく判断
"生成AI"は膨大な過去データを組み合わせた結果を出力している為、それ自体が完全に新しい独創的なアイデアを生み出すことは苦手です。
また、"生成AI"が感情がこもったような文章を出力したとしても、それは人間の微妙な感情や言葉の裏にある意図を正確に理解しているわけではなく、あくまでも蓄積されたデータを元に相応しいと思われる表現を選択・提示しているに過ぎません。
このような"生成AI"の特性を理解し、ツールとしてうまく活用していく事で、仕事の進め方をより良いものに変えていく効果が期待できます。
"生成AI"使用時のリスクと注意点
"生成AI"は適切に活用できれば便利ですが、仕事で利用するにあたっては注意すべき点があります。1つずつ見ていきましょう。
情報漏えい
"生成AI"は学習データとしてユーザーの入力情報を利用する為、顧客情報や従業員の個人情報/企業の機密情報等の重要情報を入力してしまうと、情報漏えいやプライバシー侵害のリスクが高まります。
個人情報や機密情報の漏えいを防ぐため、使っていい情報とそうでない情報はシッカリと切り分け、入力情報に関する厳格なルールを策定し、従業員に周知徹底する事が重要です。業務で使う場合は、ビジネス向けに提供されているプランやサービスを選ぶ事も大切です。
誤った情報が含まれる
"生成AI"はでたらめ・作話といった誤った情報を生成する場合があり、この現象は"ハルシネーション"と呼ばれ、もっともらしい文章が出力されるので、注意が必要です。
特に、専門性やリアルタイム性が求められる情報の精度は低くなりがちです。また、"生成AI"の学習データは最新とは限らない為、古い情報に基づいてコンテンツが生成される事も少なくありません。
出力された内容については、必ず人の目でのチェックや事実確認を行い、中身をよく精査しましょう。
不適切な表現が含まれる
"生成AI"が出力するコンテンツには、差別的な表現や偏見に基づいた内容、あるいは社会的に不適切とされる情報が含まれる可能性があります。これは、AIが学習するデータセットに社会の偏見や不正確な情報が反映されている事が原因です。
社内ルールや倫理観に基づき、複数人による確認を必ず行い、問題がある場合は必ず修正しましょう。
権利の侵害
"生成AI"が作成したコンテンツは第三者の著作物を利用している可能性があり、これが著作権の侵害と見なされる恐れがあります。なお、文化庁の現時点での見解では、"生成された画像等に既存の画像等(著作物)との類似性(創作的表現が共通していること)及び依拠性(既存の著作物をもとに創作したこと)が認められ、かつ、権利制限規定の対象外である場合は、既存の著作物の著作権侵害"となる事が明示されています。
著作権や知的財産権についての基本を理解し、"生成AI"の使用時には注意を払うと共に、法律や制度改正の動きもチェックしておきましょう。
当社の"生成AI"活用事例
当社ではこのほど、Googleが開発した"Gemini for Google Workspace"を本格的に導入しました。概要をお伝えすると共に、どのように活用しているかをご紹介します。
"Gemini for Google Workspace"とは
"Gemini for Google Workspace"とは、Googleが企業や組織向けに提供している業務効率化ソフトウェア"Google Workspace"の利用者が使える"生成AI"のサービスです。これまでは有料の拡張機能である”アドオン”という扱いでしたが、2025年01月16日から"Google Workspace"に標準搭載に切替えられました。
私たちは、"Gemini for Google Workspace"の活用促進で、より一層の業務効率化を目指します。
どんな機能があるのか
"Gmail"や"Googleドキュメント"といった"Google Workspace"の様々なアプリを使う際に、サポートツールとして役立ちます。"Gemini for Google Workspace"でできる主な作業例は以下の通りです。
- Gmail: メール文面の自動作成、メールの要約、返信案の生成、メール検索及び分析/統合等
- Googleドキュメント: 文章作成、文章校正、アイデア出し、内容の要約等
- Googleスプレッドシート: データ整理及び分析/統合等
- Googleスライド: スライドの作成支援、画像生成等
- Google Meet: 議事録の自動作成、内容の要約、字幕の翻訳等
- Googleドライブ: ファイルの検索、フォルダの要約、ファイル整理支援等
- Geminiアプリ: 情報のリサーチ及び分析/統合等
単体の"Gemini"との違い
"Gemini"は一般的な生成AIアプリで、気軽に"生成AI"を試したい人向けのサービスです。専用のWebサイトやモバイルアプリでチャットをする事でテキスト等を生成できます。
Googleアカウントがあれば誰でも無料で利用できますが、より高性能なモデルを使いたい場合は、有料版の"Gemini Advanced"も提供されています。
ただし、"Gemini"や"Gemini Advanced"は、入力したデータがサービス向上の為に利用される可能性があり、機密情報の入力は避けるべきです。
一方、"Gemini for Google Workspace"は、主にGoogleの各種アプリを使用する際に使えるアシスタント機能です。
"Google Workspace"は元々ビジネス用として提供されているサービスであり、そこに搭載された"Gemini for Google Workspace"にも、強固なセキュリティ対策とデータ保護が適用されています。
機密性が担保されており、ユーザーが入力した情報や"Gemini for Google Workspace"が生成した内容が、AIの学習に利用される事はなく、原則として勝手に外部に漏洩される事もありません。
また、設定によって"Gemini for Google Workspace"による機密データへのアクセスを制御する事も可能です。
参考:Google Workspace の生成 AI に関するプライバシー ハブ
もし、企業が"Gemini"を利用したいのであれば、安全/安心の観点からも"Gemini for Google Workspace"が最適です。
"Gemini for Google Workspace"を業務で使ってみた社員の感想
実際に"Gemini for Google Workspace"を使っている社員に、用途や使用感を伺いました。
【用途】
情報の検索、ブログの構成作成
![[JP][Blog]geminiリサーチのスクショ](https://www.daiwast.co.jp/hs-fs/hubfs/images/blog/%5BJP%5D%5BBlog%5Dgemini%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7.png?width=700&height=438&name=%5BJP%5D%5BBlog%5Dgemini%E3%83%AA%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7.png)
![[JP][Blog]Gemini_for_google_workplaceの画面](https://www.daiwast.co.jp/hs-fs/hubfs/images/blog/%5BJP%5D%5BBlog%5DGemini_for_google_workplace%E3%81%AE%E7%94%BB%E9%9D%A2.png?width=700&height=439&name=%5BJP%5D%5BBlog%5DGemini_for_google_workplace%E3%81%AE%E7%94%BB%E9%9D%A2.png)
"生成AI"に慣れるには少しずつ触れる事が大事
前述した通り、"生成AI"には様々な種類があります。
慣れる為には、興味を持った"生成AI"を無料体験で触ってみる事をオススメします。ただしその際は、守秘義務のあるデータや個人情報といった機密情報は絶対に入力しないように気をつけましょう。
抵抗感がある場合は、まずは簡単な"遊び"から始めてみるのはいかがでしょうか。以下のブログ記事では、無料版の"ChatGPT"と社員がしりとりをしてみた話題をご紹介しています。ぜひこちらも併せてご覧ください。
![[JP]chatGPT使ってみたキービジュ](https://www.daiwast.co.jp/hs-fs/hubfs/images/blog/%EF%BC%BBJP%EF%BC%BDchatGPT%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5.png?width=350&height=163&name=%EF%BC%BBJP%EF%BC%BDchatGPT%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5.png) ブログ:"ChatGPT"って一体何ができるの?!実際に使ってみた感想を詳しくレポート。
ブログ:"ChatGPT"って一体何ができるの?!実際に使ってみた感想を詳しくレポート。
また具体的に業務で活用する際は、会社としてシッカリと利用規約を整備すると共に、必要な基礎知識を教育した上で利用を開始すると共に、ニーズに応じた学習の機会や、変化に応じてアップデートを行い、利用者一人ひとりが安心できる環境を整備する事が極めて重要です。
まとめ
今回は、"生成AI"の概要や当社の社員による感想、導入時の注意点等についてお伝えしました。
"生成AI"を取り入れれば業務効率化が期待できますが、情報の正確性や著作権、セキュリティといった問題も存在します。
"生成AI"を安全/安心かつ効果的に活用する為には、リスクや注意点を認識した上で適切に運用し、最新技術動向の把握に努める事が大切です。
ブログに対するご意見やご感想、ご質問等がございましたら、以下のページよりお気軽にご連絡ください。
最後までお読みいただき感謝申し上げます。大和鋼管ではこれからも、皆さまの為になるお役立ちの情報発信を続けてまいりますので、ご支援/ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
執筆者紹介

- タグ:
- コラム

![[JP]ブログを無料で購読する](https://no-cache.hubspot.com/cta/default/8005843/interactive-168648084244.png)